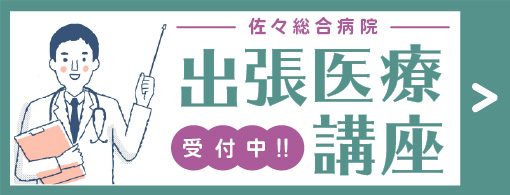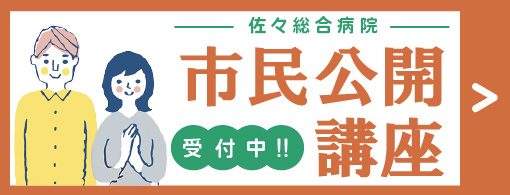胆嚢の働き
胆嚢は右上腹部にある袋状の臓器で、肝臓で作られている胆汁を貯めておく働きをしています。胆汁中には脂肪分の消化に役立つ胆汁酸やコレステロールなどが含まれますが、胆汁中のコレステロールが多くなると結晶化して石になります。胆嚢結石の7割ほどがコレステロール結石と言われています。また、コレステロールが胆嚢粘膜に付着するとコレステロールポリープになります。
胆嚢結石・胆嚢炎・胆嚢ポリープによる症状
・無症状
胆嚢結石の多くは無症候性で、検診の腹部超音波などで偶然発見されます。下記のような症状がない胆嚢結石は基本的に経過観察で大丈夫です。ただし結石充満胆嚢など胆嚢癌が否定できない場合は手術が選択肢となりますので、一度ご相談にいらしてください。
また、胆嚢ポリープについては通常症状がありませんが、大きさが10mmを超える場合やサイズが増大傾向の時などは癌が紛れていることがありますので、手術の相談が必要です。
・右上腹部痛
胆嚢の出口に石が詰まると激しい右上腹部痛をきたすことがあります。食後に多く、胆石発作の場合1−2時間程度続きます。右上腹部痛が持続したり熱が出たりした場合、炎症を伴い胆嚢炎となっている場合があります。
胆石発作の場合は急いで処置を行う必要はありませんが、胆嚢炎の場合は後述のような治療が必要になります。一般に時間が経つと重症度が上がっていきますので、我慢せずに早めに受診してください。
・黄疸
胆石が総胆管に落ち、総胆管結石や胆管炎をきたすと黄疸が出ることがあります。肌の色が黄色くなったことや、尿の色が黄色くなったことで気づかれることが多いです。血液検査上はビリルビンという値が上がることでわかります。超音波・CT・MRIなどの検査により総胆管結石が原因となっていることが分かった場合には、内視鏡的逆行性胆管膵管造影(ERCP)を行いステント留置などにより減黄をはかります。
胆嚢結石・胆嚢ポリープの診断・治療について
身体所見・腹部超音波・CT・MRI・血液検査などにより総合的に判断します。
治療適応の場合、手術が第一選択です。胆石を溶かすような薬や体外衝撃波で胆石を砕く治療は存在はしますが、ごく一部の結石にしか効果がありません。
胆嚢炎の診断・治療について
胆嚢炎は、A局所の炎症症状(右上腹部痛など)、B全身の炎症所見(発熱、採血結果など)、C急性胆嚢炎の特徴的画像所見(エコー・CT・MRIなど)から総合的に診断され、程度によってGradeⅠ〜Ⅲまでの3段階に分類されます。
GradeⅠ(軽症)の場合、基本的には早期の手術が第一選択となります。手術リスクの高い方の場合やご本人がご希望されない場合は抗菌薬投与による保存的加療を選択することもあります。
GradeⅡ(中等症)の場合、抗菌薬投与による初期治療を行なった上で、発症からの時期や全身状態によって早期手術あるいは胆嚢ドレナージを選択します。
GradeⅢ(重症)の場合は他の臓器障害を伴いますので、抗菌薬による治療を始めながら全身管理が必要になります。治療に反応する場合は早期手術を行うこともありますが、手術に耐えられない状況と考えられる場合には胆嚢ドレナージを選択します。
手術について
当院では基本的に腹腔鏡下胆嚢摘出術を行なっています。(癌を疑う場合や炎症が非常に強い場合などでは始めから開腹手術を選択することもあります。)
腹部に4箇所の穴を開け、医療用のカメラでお腹の中を覗きながら胆嚢を摘出します。
小さな傷で行うことで術後の回復が早くなります。

手術時間は1−2時間程度(+麻酔時間)、入院期間は4―5日間程度です。
合併症としては、出血 隣接臓器の損傷(特に胆管損傷) 胆汁漏 腹腔内膿瘍 創感染 腸閉塞などがあります。
手術のスケジュールについて
以下に胆嚢結石症に対する予定手術のスケジュールを示します。
胆嚢炎の場合は炎症が落ち着くまで治療が必要になりますので、入院期間は延長することが多いです。
| 手術前日 | 手術日 | 手術翌日 | 2日目以降 | |
| 処置・検査など | 午後入院
翌日の手術時間は この日にお伝えします。 |
手術 | 血液検査・レントゲン検査
お腹に管が入っている場合には 抜去を検討します。 |
経過良好の場合退院可 |
| 安静度 | 制限なし | 術後はベット上安静 | 朝回診後〜制限なし
適宜痛み止めを使います。 |
制限なし |
| 食事 | 夕方まで摂取可 | 朝まで飲水可、
その後絶飲食 |
昼から食事開始 | 制限なし |
退院後は外来にて創部の確認を行い、胆嚢の病理結果(1%程度の方に偶然胆嚢癌がみつかります)をお伝えします。経過良好であれば術後の通院は1度きりで、定期的な通院は不要です。
経皮経管胆嚢ドレナージ(PTGBD)について
主に手術適応ではない急性胆嚢炎の場合や一部の下部胆管閉塞の場合に行います。
胆嚢を超音波で確認しながら針を刺し、チューブを留置して胆嚢内の胆汁を体外に出す治療です。


合併症として、出血、感染症、気胸や胸水(経胸膜的穿刺による)、胆汁性腹膜炎(お腹の中に胆汁が漏れることによる)などがあります。
入院期間は胆嚢炎の場合で10日間程度で、チューブを挿入したまま退院の上、炎症がすっかり落ち着いた2−3ヶ月後に待機的手術を計画します。手術を行わない場合やチューブの管理が出来ない場合などで早期に抜くこともありますが、胆嚢炎の再燃や胆汁性腹膜炎をきたす場合があり、時期については相談が必要です。